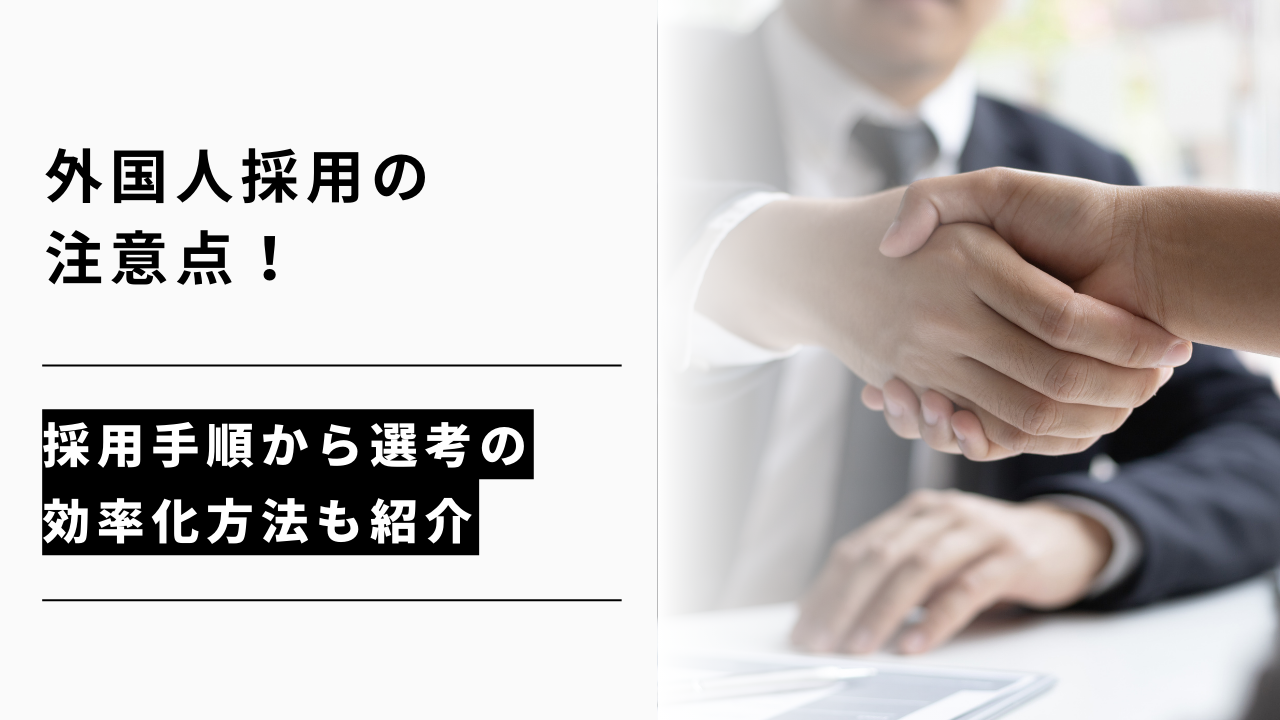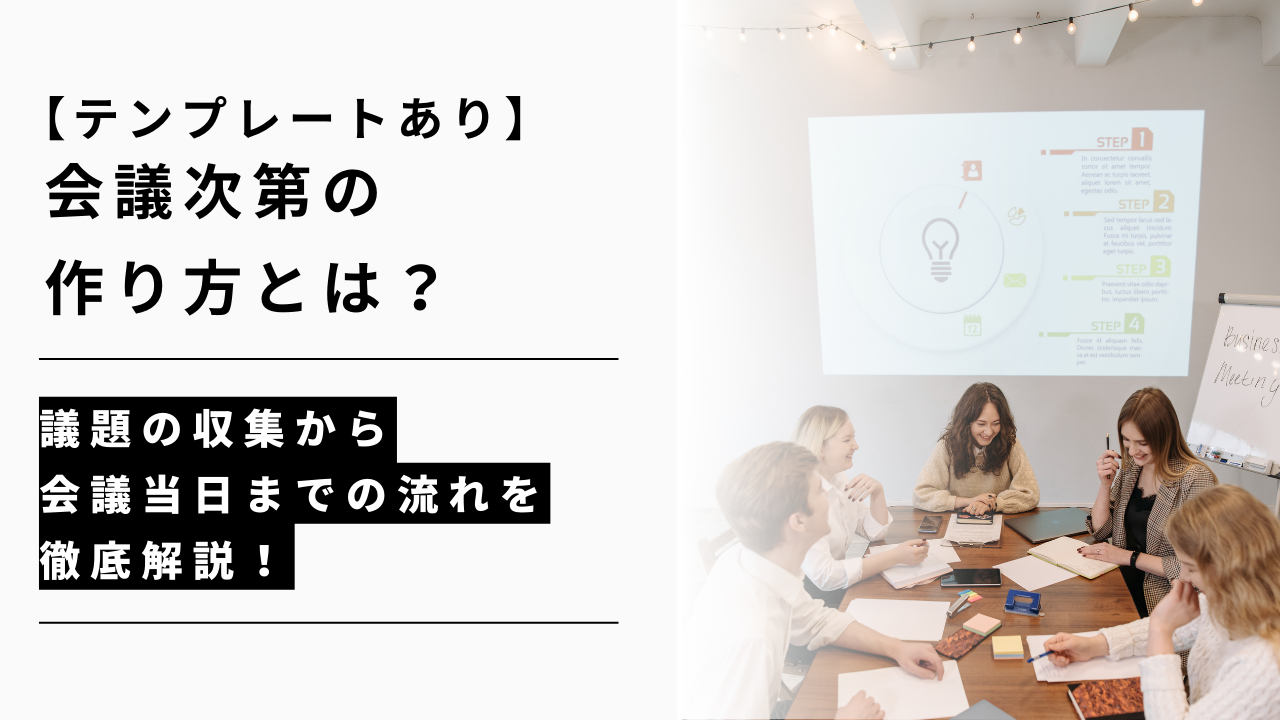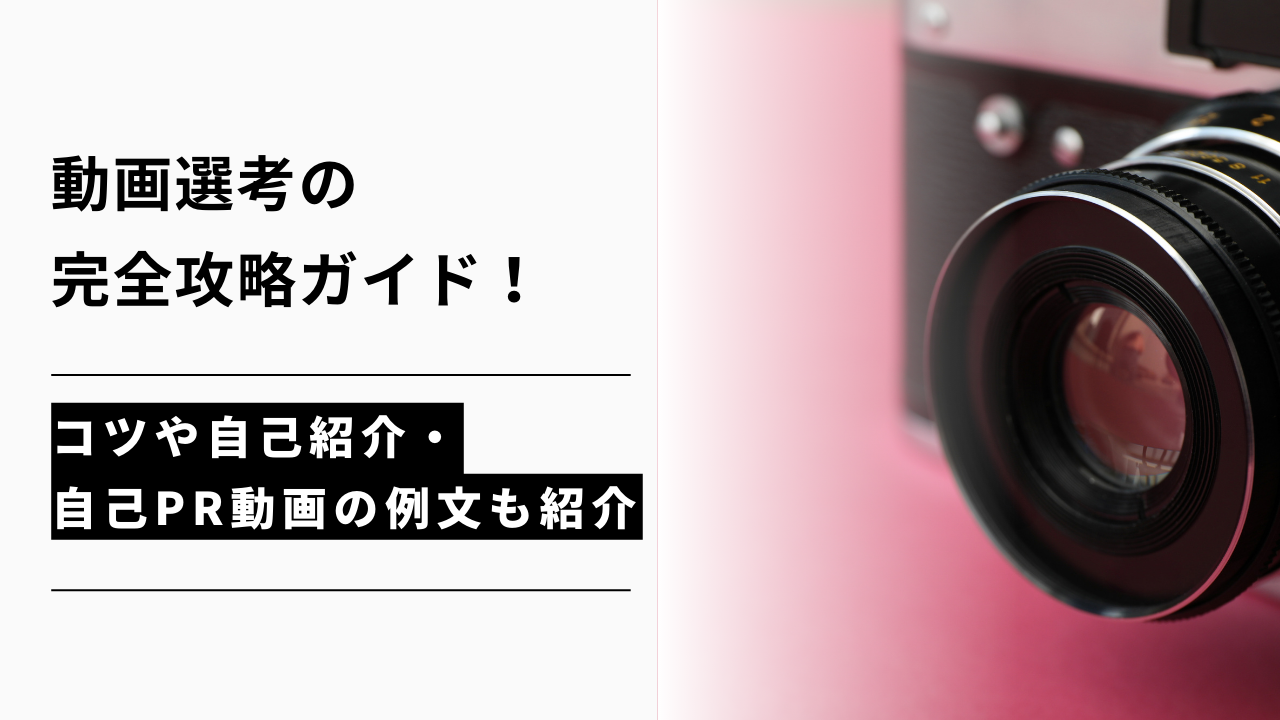一覧に戻る
録画面接とは?企業にとってのメリットや導入のポイントを解説!
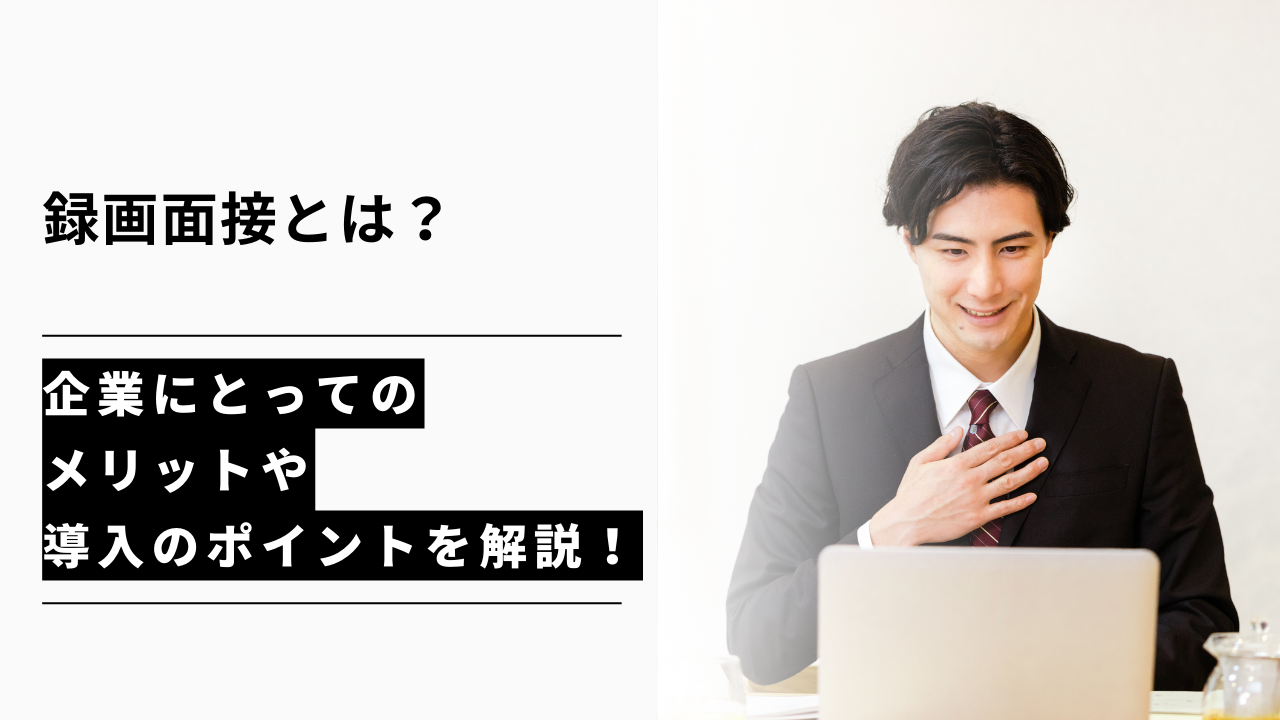
近年、大手企業を中心に録画面接の導入が進んでおり、効率的な採用手法として注目を集めています。
録画面接のメリットは従来の対面面接やオンライン面接と比べて、時間やコストを大幅に削減し、書類では把握できない応募者の本質を評価できることです。
本記事では、録画面接の基本的な流れやメリットを詳しく解説するだけでなく、具体的な導入のコツについても紹介します。
効率だけでなく採用の質も向上させたいと考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
録画面接とは
録画面接とは、応募者が企業側で用意した質問に回答する様子を自身でビデオ録画し、撮影した録画データを企業に提出する形式の選考方法です。
企業側は、録画された回答を任意のタイミングで視聴できるため、効率的に選考を進められます。また、応募者にとっても、事前に質問内容を確認したうえで録画に臨めるため、準備を整えた状態での回答が可能です。
上記の特徴から、録画面接は企業と応募者の双方にとって負担を軽減する新しい選考スタイルとして注目されています。
録画面接とWeb面接の違い
先述のとおり、録画面接では応募者が十分に準備を整えたうえで取り組むことが可能です。企業側も録画データを必要に応じて何度でも確認でき、じっくりと時間をかけて評価できます。
ただし、企業側が応募者に対して、リアルタイムでの質問の深掘りや反応を直接観察することは難しいという制約があります。
一方、Web面接はリアルタイムのやり取りが可能で、応募者のコミュニケーション能力や柔軟性をその場で確認できるのが大きな特長です。
しかし、Web面接ではスケジュール調整が必要となり、双方の時間的な負担が生じる可能性があります。
採用方法を検討する際は、それぞれの選考方法の特性を理解し、採用の目的に応じて最適な方法を選択することが重要です。
録画面接が注目される理由
近年、録画面接が注目されている理由として、以下の3つが挙げられます。
導入が簡単
企業側の人材不足や採用コスト削減
大手企業を中心に導入が拡大
それぞれ詳しく見ていきましょう。
導入が簡単
新しい仕組みの導入には慎重になる企業も少なくありませんが、録画面接は専用のツールを活用することで、導入が簡単に行えます。
専用ツールを活用することで、応募者も企業側も複雑な準備をすることなく利用可能です。
さらに多くのツールが応募者への質問設定やデータ管理の機能を備えており、採用を効率良く進められます。
また、初期設定や操作方法に関するサポート体制が整ったツールも多いため、ITに詳しくない採用担当者でも安心して活用可能です。
企業側の人材不足や採用コスト削減
多くの企業が人手不足や採用コストの増加といった課題に直面するなかで、録画面接は効率的な採用方法として活用されています。
通常の対面面接やリアルタイムで行うWeb面接では、応募者と企業側のスケジュール調整が必要です。特に面接官がほかの業務を抱えている場合、予定の確保が大きな負担となるでしょう。
しかし、録画面接では面接官は都合の良い時間に動画を確認できるため、効率的な運用が可能です。また、録画内容をまとめて視聴することで面接時間を短縮し、選考の流れをスムーズに進められます。
さらに、交通費や会場費といったコスト削減の効果もあり、限られたリソースのなかでも採用活動を進めやすいのが録画面接の特徴です。
大手企業を中心に導入が拡大
デジタル化の進展に伴い、効率的な採用を実現する手段として、大手企業を中心に録画面接の導入が拡大しています。
大手企業では、採用プロセスの効率化やコスト削減といった成果が現れ、録画面接の成功事例が注目を集めています。結果として、録画面接は新たな選考方法としてほかの企業にも関心を持たれるようになりました。
特に、激化する人材確保の競争に対応し、質の高い選考を効率的に行いたい企業にとって、録画面接は非常に魅力的な手法と言えるでしょう。現在では、録画面接の利便性や効果が評価され、中小企業にも導入が広がりつつあります。
録画面接のやり方や流れ
録画面接は主に以下の3つの流れで進めます。
録画面接の案内を送付
応募者が動画を撮影
企業側が動画を確認し評価する
上記の流れについて詳しく解説しますので順に見ていきましょう。
1.録画面接の案内を送付
録画面接を実施する際は、応募者に対して録画面接の目的や具体的な流れを記載した案内を送付します。
案内には、応募者が安心して取り組めるように質問内容や回答方法、使用するシステムの操作手順を詳しく説明します。また、回答にかけられる時間の目安や推奨されるインターネットの環境についても具体的に記載することが大切です。
さらに、応募者がスムーズに準備を進められるようにカメラやマイクの確認手順を含めたシステムのサポート情報を提供すると効果的です。応募者がシステム面での不安を軽減し、本来の実力を発揮できる環境を整えられるでしょう。
2.応募者が動画を撮影
応募者が企業から指定された質問にもとづき、自分のタイミングで動画を撮影します。
応募者は事前に録画に関する案内を確認してから動画を撮影し、システムをとおしてアップロードします。多くの録画面接ツールには録画をやり直す機能があるため、応募者が納得の行く状態で回答を提出することが可能です。
応募者が納得の行く形で動画を提出することで、企業は応募者の能力や考えをより正確に評価できるでしょう。
3.企業側が動画を確認し評価する
応募者から提出された動画を面接官が確認し、定められた評価基準に基づいて審査を行います。動画は専用のシステムを通じて複数の面接官と共有されるため、それぞれが独自に視聴し、評価を行うことが可能です。
面接官は応募者の回答内容をもとに、質問への適切な対応や表現力などを確認し、評価シートを活用して点数やコメントを記録します。評価を行う際は、事前に企業内で統一された基準を元に判断を行うことが重要です。
評価が完了したら結果を集約し、次の選考に進む応募者を決定します。場合によってはフィードバックを作成し、応募者に共有する準備を進めます。
録画面接を行うメリット
録画面接のメリットとして挙げられるのは主に以下の4つです。
面接辞退や日程調整の手間を削減
面接内容を複数の面接官が確認可能
書類ではわからない応募者の本質を把握
海外在住の候補者面接がスムーズに
それぞれ詳しく見ていきましょう。
面接辞退や日程調整の手間を削減
録画面接では、応募者と面接官のスケジュール調整が不要です。
通常の対面面接やWeb面接では、双方のスケジュールを合わせる手間が発生し、急な自体や日程変更があった場合には再調整が必要となるなど、採用活動に大きな影響を及ぼします。
一方で録画面接では、応募者が指定された期限までに動画を撮影・提出するだけで良いため、スケジュール調整の負担が発生しません。
さらに応募者が締切日までに動画を提出しなかった場合でも「締切日までに提出がない場合は辞退とみなします」と事前に伝えておくことで、効率的に選考を進められます。
面接辞退が発生した場合でも、録画面接では事前準備が少なく済むため、無駄になるリソースを最小限に抑えられます。
面接内容を複数の面接官が確認可能
録画面接では、複数の面接官が動画の内容を確認できる点も大きなメリットです。
録画されたデータはパソコンやスマートフォンを使って共有できるため、面接官それぞれが自身のスケジュールに合わせて確認できます。出張中や遠方にいる面接官でも簡単に内容を確認でき、場所や時間に制約されません。
さらに録画データは何度でも見返せるため、対面の面接では見逃しがちな応募者の表情や回答内容を再確認できます。録画データを複数の面接官が確認し、何度も見返すことにより、より正確で公平な評価ができるでしょう。
また、業務の都合で確認が遅れた場合でも、後日改めて内容をチェックできるため、スケジュールの調整が必要な対面面接やWeb面接に比べて柔軟性が高まります。
書類ではわからない応募者の本質を把握
録画面接では、履歴書やエントリーシートだけではわからない応募者の人柄や本質を把握できます。
応募者が自分で撮影した動画をとおして、話し方や表情、声のトーン、価値観など、文字情報では得られない多くの情報を確認できるでしょう。
動画には応募者の素の部分が表れやすい傾向があり、回答の内容だけでなくコミュニケーションスキルや誠実さなど、人物像をより詳細に理解することが可能です。
さらに、動画の背景や撮影環境などからも応募者の生活スタイルや性格が把握できる場合もあります。
海外在住の候補者面接がスムーズに
録画面接は、海外在住の応募者との選考をスムーズに進められます。
時差のある海外在住の候補者ともリアルタイムでのスケジュール調整を行う必要がなく、応募者は自身の都合に合わせて動画を撮影・提出できます。録画面接の導入により、距離や時差の問題を気にすることなく、効率的に選考を進めることが可能です。
さらに、遠方から面接会場に足を運ぶ必要がないため、応募者の心理的負担や交通費の負担を軽減でき、気になっていた企業へ気軽に応募しやすくなります。録画面接を採用することで、地理的な制約に関係なく、優秀な人材を幅広く確保することが可能です。
録画面接を行うデメリット
録画面接には多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。主なデメリットとして以下の3つが挙げられます。
リアルタイムで深掘りできない
機材トラブルや録画ミスのリスク
求職者が応募をためらう恐れがある
録画面接を導入する際には、メリットとデメリットを正しく把握したうえで活用していきましょう。
リアルタイムで深掘りできない
録画面接の課題の1つは、リアルタイムでの深掘りができない点です。応募者の回答が事前に録画されたデータであるため、面接官がその場で追加の質問をしたり、回答内容を掘り下げたりするコミュニケーションが取れません。
録画された動画をもとに応募者の人柄や対応力を評価する必要があるため、対面の面接に比べて評価の難易度が高く感じられることもあるでしょう。
録画面接を活用する際には、質問内容を慎重に設定し評価基準を明確にするなど、選考の精度を高める工夫が必要です。
機材トラブルや録画ミスのリスク
録画面接では、機材トラブルや録画ミスが発生するリスクを考慮する必要があります。
応募者が自身のデバイスやネット環境を使用して録画を行うため、端末の不具合や音声が途切れるといった問題が起こる可能性があります。また、企業側のシステムトラブルや、映像データ送信時のファイル破損も選考を滞らせる原因になり得るでしょう。
上記のリスクを軽減するためには、応募者に対して録画機材の仕様や推奨されるファイル形式、送信方法について事前に説明することが重要です。
さらに、トラブル発生時の対処手順をあらかじめ共有しておくことで、万が一の際にも迅速に対応できるでしょう。
求職者が応募をためらう恐れがある
録画面接は比較的新しい面接方法であるため、不慣れな求職者が応募をためらう可能性があります。
特に、録画面接に対する苦手意識を持つ求職者は少なくありません。苦手意識を持つ理由として、撮り直しの手間や1人で話すことへの抵抗感、手ごたえを感じづらい点などが挙げられます。
求職者の心理的ハードルを下げるためには、企業側が録画面接の一連の流れや使用するシステムの操作方法をわかりやすく説明することが重要です。応募フォームや案内資料に、録画手順や準備に必要な情報を丁寧に記載することで、安心感を与えられます。
録画面接の導入のコツ5選
録画面接を効果的に活用するには、以下の5つのコツを押さえることが重要です。
導入目的を明確にする
質問を適切に設計する
応募者にガイドラインを提供する
技術サポートを用意する
フィードバックを収集する
それぞれ詳しく解説します。
導入目的を明確にする
録画面接を導入する際には、目的を明確にし、採用担当者全員に共有することが重要です。
なぜ録画面接を導入するのか理由を関係者間で共有することで、導入プロセスでの混乱を最小限に抑え、面接官のモチベーション低下を防げます。
例えば全国各地から幅広く応募者を募る必要がある場合や、多数の求職者を効率的に選考する目的がある場合など、録画面接を行うことのメリットを説明し、共通の理解を得ることが大切です。
導入目的が不明確なまま進めると、面接官が従来の面接方法に固執し、新しいシステムを活用しきれない可能性があります。
導入目的を全員で共有し、選考の効率や質の向上を実現できる体制を構築しましょう。
質問を適切に設計する
録画面接では求める人材像にもとづいた適切な質問の設計がポイントです。
職種や役職、社風に応じて「どのようなスキルや特性を持つ人材が必要か」を具体化し、条件に合わせて質問内容を作成する必要があります。
録画面接では応募者の回答や映像が評価対象となるため、評価基準が不明確だと面接官ごとの主観が結果に影響を与え、ミスマッチが起きやすくなります。ミスマッチを防ぐためにも、質問ごとに評価項目や採点基準をあらかじめ設定し、関係者全員で共有することが重要です。
例えば、コミュニケーションスキルを確認するための質問や、具体的な状況に対する行動を問うシナリオ形式の質問を用意することで、応募者の特性を効果的に引き出せます。
録画面接の精度を高めるには、適切な質問設計がポイントです。
応募者にガイドラインを提供する
録画面接をスムーズに進めるためには、応募者向けにわかりやすいガイドラインを提供することが不可欠です。
録画面接はまだ一般的な手法とは言えず、自分の動画を撮影する経験がない応募者にとっては不安や戸惑いを感じやすいでしょう。求職者が応募自体を躊躇してしまう可能性があります。
企業は録画面接の目的やメリットを応募者にも明確に伝え、安心して取り組める環境を整えることが重要です。動画の内容やフォーマット、適切な服装や背景など具体的な撮影ガイドラインを提供しましょう。
さらに動画撮影の基本的なコツやサンプル動画を共有することで、応募者が自信を持って録画に挑戦できます。
また、質問を気軽に相談できる窓口を設けることも効果的です。応募者がポジティブな姿勢で録画面接に臨めるだけでなく、企業側もより適切な人材を見つけられます。
技術サポートを用意する
技術サポートを充実させ、トラブルを最小限に押さえることも重要です。
応募者の録画環境やネット環境に不具合がある場合や、企業側のシステムトラブルが発生した場合には選考が滞る可能性があります。機材や通信の不具合が起こるリスクを軽減するため、企業は事前に技術サポート体制を整えておく必要があります。
応募者に対しては、録画システムの利用方法や推奨される機材・環境をわかりやすく説明しましょう。また、トラブルが発生した際に問い合わせができる窓口を設けると、応募者が不安なく録画面接に取り組めます。
企業側では録画面接のシステムや通信環境のテストを徹底し、関係者が技術的な問題にすぐに対応できる環境を整えます。技術サポートを用意することで、応募者と企業の双方が円滑に録画面接を進められるでしょう。
フィードバックを収集する
録画面接を効果的に運用するためには、応募者や面接官からのフィードバックを定期的に収集し、選考内容や運用プロセスを改善することが大切です。
録画面接は比較的新しい採用手法であるため、導入後の運用段階で課題が浮き彫りになる場合があります。
応募者からは録画面接の使いやすさや質問内容の適切さ、システムの操作性について意見を集め、面接官からは評価基準のわかりやすさや動画確認時の効率性などについて感想を聞くことで、選考全体の改善点を把握できます。
収集した意見をもとに質問の設計を見直したりシステムの使い勝手を向上させたりすることで、応募者や面接官の負担軽減や、選考の精度向上にも繋がるでしょう。
採用を効率化するなら『Rimo Voice』
録画面接は対面やWeb面接と比べて効率的に採用を進めることが可能です。
しかし、応募者の動画を一つひとつ丁寧に確認するには時間と労力が必要で、面接官にとって大きな負担となるでしょう。複数の応募者を比較する際、発言内容や回答のポイントを整理するのに苦労することも少なくありません。
『Rimo Voice』であれば、応募者が提出した動画を自動で文字起こしし、発言の要点を整理してくれるため、面接官の負担を大幅に軽減します。
初期段階では動画をとおして応募者の話し方や表情、コミュニケーションスキルを確認します。次に『Rimo Voice』の文字起こしデータで内容を深掘りすることでより効率的な評価が可能です。
『Rimo Voice』では無料トライアルも実施しています。録画面接を効率化させたい採用担当の方はぜひ試してみてください。
録画面接の導入で採用プロセスの質を向上させよう!
録画面接は、応募者が企業の質問にもとづいて回答を録画し、提出する新しい選考方法です。
スケジュール調整の負担を軽減し、録画データを複数の面接官が確認できるため、効率的かつ公平な選考が可能です。また、応募者の話し方や表情、価値観など、書類ではわからない情報を把握できる点が魅力と言えます。
一方でリアルタイムでの深掘りが難しいことや、動画撮影に不慣れな求職者が応募を躊躇うといった課題もあります。
上記の課題を解決するためにも、本記事で紹介した導入のコツを押さえながら採用を進めることが重要です。
録画面接を適切に運用し、採用の効率化と質の向上を実現させましょう。
関連記事
一覧に戻る