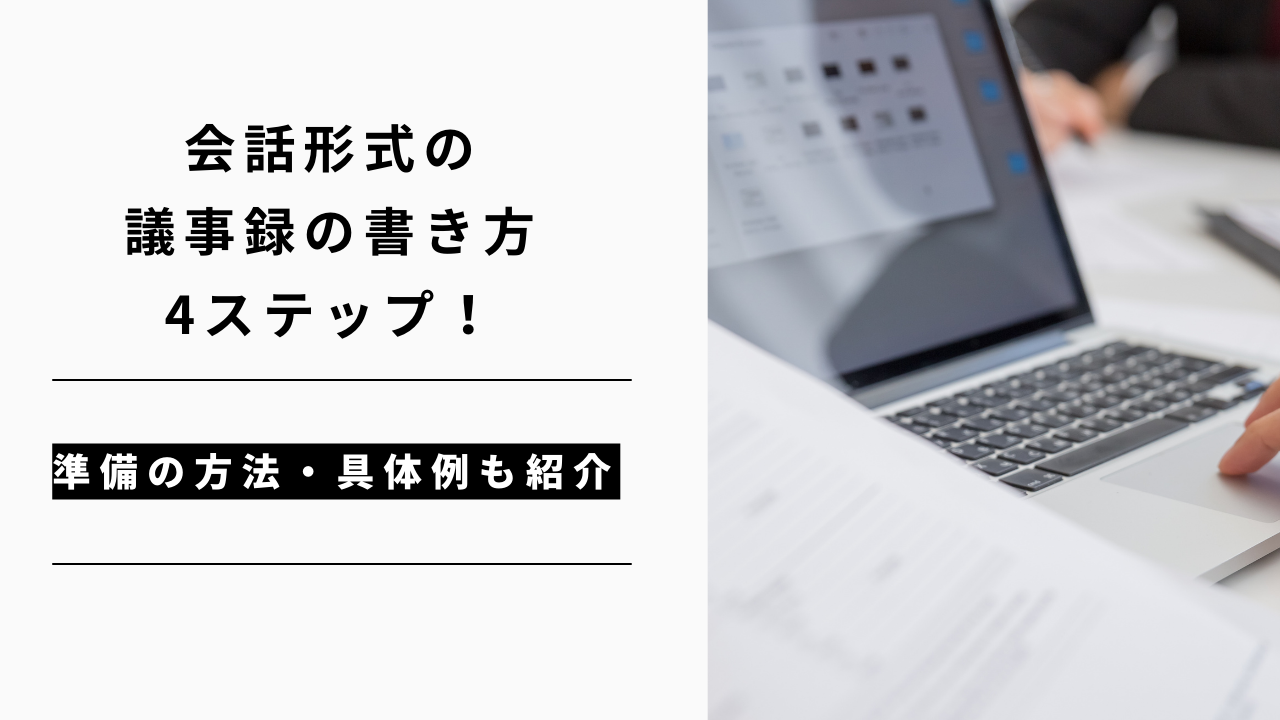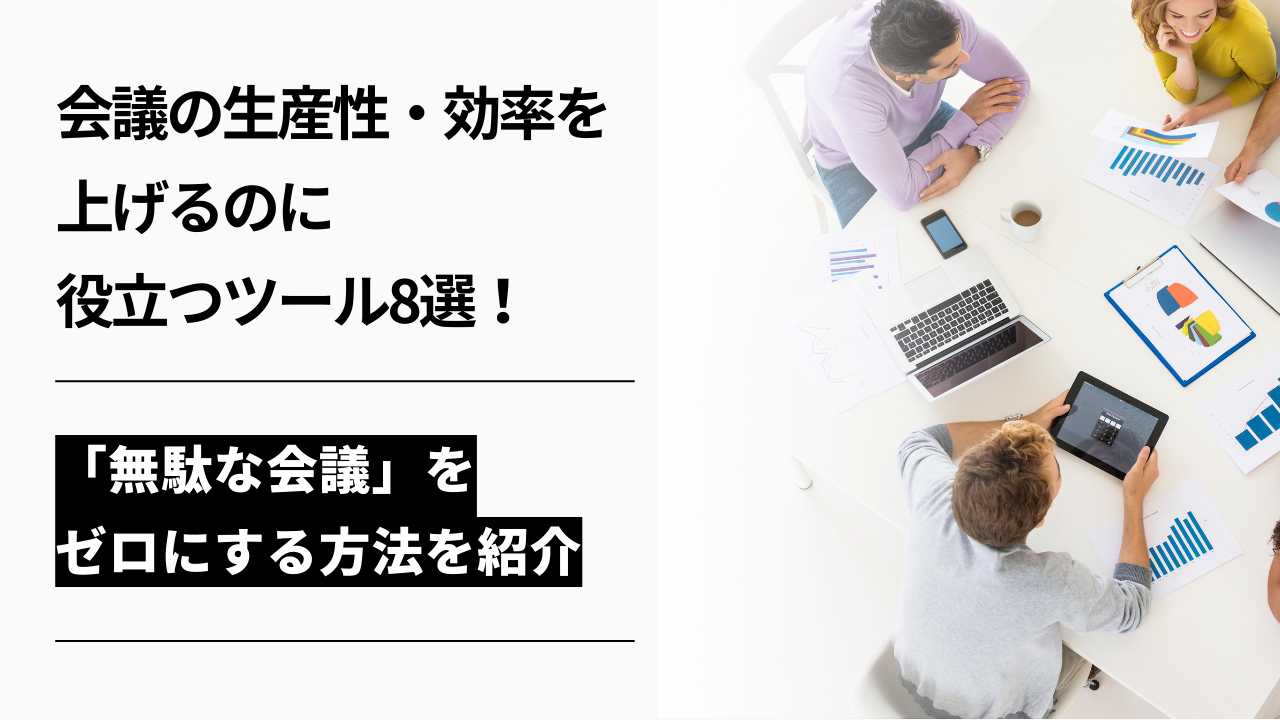一覧に戻る
【例文集あり】会議の司会は準備が大切!進行のコツとチェックリストを解説

会議の進行役を任されて、「ちゃんと仕切れるだろうか…」「何を話せばいいんだろう」と不安になる方が多いのではないでしょうか。
会議をスムーズに進めるためには、上手に話す力よりも、事前準備が大切です。
この記事では、会議の司会進行の役割や必要なスキル、事前に整えておくべき準備、当日に意識すべきポイントを解説します。
この記事を読むことで、会議までに何を準備すれば良いかが明確になり、自信を持って会議に臨めるようになります。
記事後半では、実際に使える例文集も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
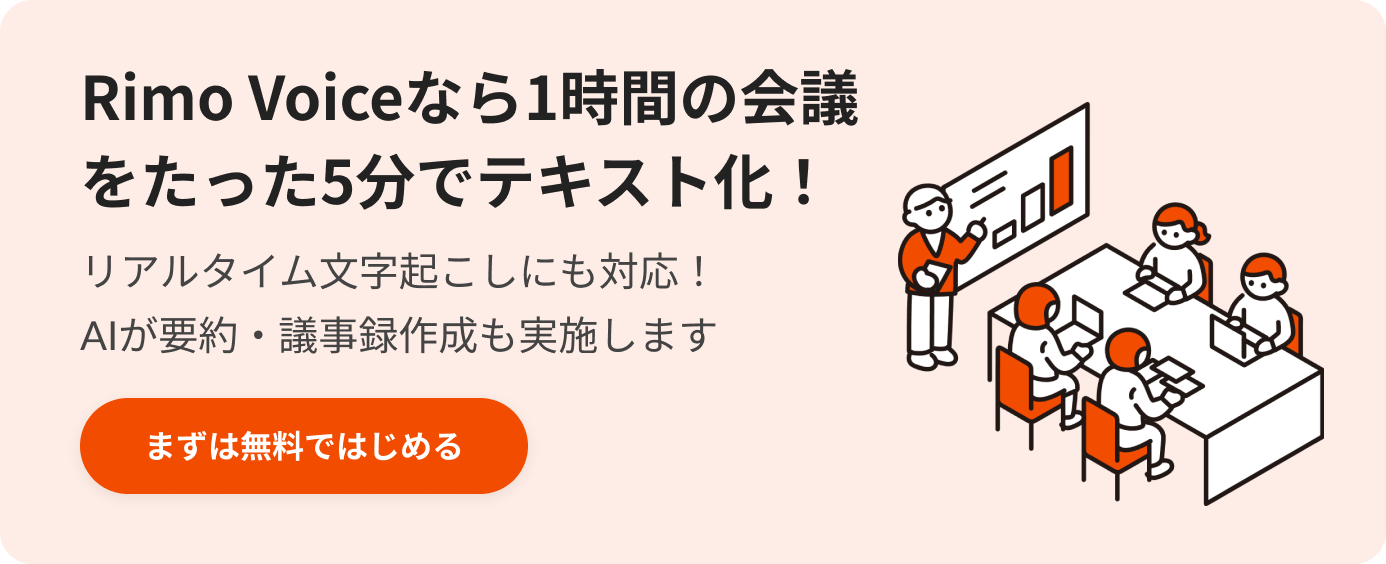
会議の司会進行の役割とは?

会議の進行役は、一般的に「ファシリテーター」とも呼ばれます。
単に会議を開始して終わらせるのではなく、議論を円滑に進め、参加者の意見を引き出し、最終的な結論へ導かなければなりません。
具体的には、以下のような役割を担います。
会議の流れを管理し、予定時間内に収める
発言が偏らないよう、参加者全員から意見を引き出す
複数の意見を整理・要約して議論をまとめる
対立や脱線が起きた際には中立的な立場で調整し、議題に戻す
会議の司会進行役には「場を回す」広い視点が求められます。
会議の雰囲気をつくり出しながら議論を活性化させ、成果へとつなげることが、会議の進行役(ファシリテーター)の役割です。
会議の司会進行に必要なスキル
会議を円滑に進めるためには、次の4つを意識して進行しましょう。
時間を管理する力:会議を予定時間内に収める
傾聴力:参加者の意見を丁寧に聞き取る
要約力:出てきた意見をまとめる
質問力:参加者から良い意見を引き出す
調整力:発言が偏らないようにする、対立や脱線を修正する
これらを意識することで、会議が円滑に進み、参加者が納得する結論を出しやすくなります。
進行役は中立的な立場で、議論が活発に行われる環境を作ることが大切です。
会議をスムーズに進行するには「準備」が大切
会議を成功させるために最も重要なのは、事前準備です。
準備をしておくことで、余裕を持って会議の場を回せるため、参加者の意見も引き出しやすくなります。
会議を円滑に進めるために、次の4つの準備をしておきましょう。
これらを押さえておけば、当日の進行に自信を持って臨めます。
時間配分を考える
限られた時間で結論を出すには、あらかじめ議題ごとの時間配分を設定しておくことが大切です。
例えば、「この議題は30分」「最後の10分はまとめに充てる」といった目安を決めておくと、当日の進行状況を把握しやすくなり、時間超過を防げます。
逆に時間の見通しがないまま会議を始めてしまうと、議論が長引いたり脱線したりして、結論が出ないまま終了してしまう場合もあります。
進行役はタイムキーパーとしての役割も担い、時間内に結論を出せるように、会議を進めていきましょう。
台本を作成する
台本を作成しておけば、会議の流れが明確になり、「当日、何をどう話そう...」という不安がなくなります。
台本とはいえ、一字一句を暗記する必要はありませんが、大まかな流れは整理しておきましょう。
冒頭の挨拶
議題の順番
意見を促すタイミング
まとめの言葉 など
事前に台本を作成しておくことで、当日は落ち着いて会議を進められ、想定外の場面にも余裕を持って対応できます。
参加しやすい雰囲気を作る
会議をスムーズに進めるためには、参加者が意見を出しやすい雰囲気を整えることも大切です。
発言が少なく、一部の人だけが話す状況では、良い会議にはなりません。このような場面を避けるためにも、進行役は次のような工夫をしましょう。
発言には頷きや相槌を返して安心感を与える
発言が少ない人にさりげなく声をかける
否定から入らず、まずは意見を受け止める
「時間だけかかるのに何も決まらない会議」では、次回以降の参加意欲が下がってしまいます。
多くの人から意見を集め、有意義な会議にすることで、参加者の満足度も高まります。進行役は雰囲気作りも意識して、全員が発言しやすい場を作りましょう。
会議後の議事録作成の準備をしておく
会議は話し合って終わりではなく、決定事項や議論の内容を参加者に共有することまでが一連の流れです。そのため、進行役は会議前から「議事録をどう残すか」を意識しておくと会議後の流れがスムーズになります。
具体的には、以下のような準備をしておきましょう。
議事録用のフォーマットを用意しておく
発言者や担当タスクを記録する欄を作っておく
録音や文字起こしツールを使えるようにしておく
共有が素早く行えることで、決定事項の認識のズレを防ぎ、次のアクションにも素早く移れます。
なお、『Rimo Voice』を活用すれば、会議内容の文字起こしとAIによる要約で、効率的に議事録を作成可能です。
他にも、これらの機能に加えて、次のような特徴があります。
ツールでそのまま録音・リアルタイム文字起こし
AIチャットで会議中の聞き逃しを防止
ZoomなどのWeb会議ツールと連携
複数人で同時に議事録を編集
『Rimo Voice』は7日間の無料トライアルが用意しているため、関心のある方はぜひ気軽にお試しください。
登録には Googleアカウント・Microsoftアカウント・メールアドレスのいずれかが必要です。クレジットカードの登録は不要で、トライアル終了後は自動的に解約されるため安心して利用できます。
会議の司会進行を任されたら準備すること7ステップ

会議の司会進行を任されたら、当日までに以下の手順で準備をしてください。
会議を成功させるために必要な7ステップを詳しく解説します。
1. 目的・議題・ゴールを決定
まずは会議の目的・議題・ゴールを設定しましょう。
会議の目的を明確にすることで、参加者の意識が揃った良い会議になります。
その目的を達成するために話し合う内容が議題です。議題が多いと目的がぶれてしまうので、多くても5つ程度としてください。
今回の会議で決定すべき事項や方向性といったゴールを描いた上で、会議に挑みましょう。
目的や議題、ゴールを決める際に参考にしたいのが、主に以下の3つに分類される会議の種類です。
認識の共有会議(例:報連相)
意見収集会議(例:商品開発)
意思決定会議(例:プロジェクトの方針決め)
目的や議題、目指すべきゴールは会議の内容によって異なります。
それぞれの内容に適したものを設定し、円滑に会議を運営しましょう。
2. 参加者の日程調整
参加者が会議に参加可能な日時を調整します。
候補日時をいくつか提案して予定を合わせましょう。
他の会議や社内イベントと重ならないよう、あらかじめ把握できる予定がある日時は避けてください。
会議の日時が決まったら参加者に連絡し、出欠確認をしましょう。
3. 設備予約
会議の日時が決まったら、使用するパソコンや会議室を予約します。
会議室は準備や後片付けも考慮し、前後30分ほど余裕を持って予約しておくと安心です。
また、会議室を選ぶ際には以下のポイントを意識しましょう。
参加人数に合った広さ:参加者が入り切れるか、広すぎないか
設備の充実度:プロジェクター・モニター・ホワイトボード・マイク・スピーカーなどが使えるか
アクセスのしやすさ:社内外からでも参加しやすい場所を選ぶ
オンライン会議対応:Wi-Fi環境やカメラ・マイク設備が整っているか
状況によっては社外の貸会議室を利用するのも一つの手です。貸会議室なら時間が区切られているため、会議がダラダラと長引くのを防げます。
4. 会議資料の作成
議事次第や関連資料を作成します。
会議資料は2日前を目処に、事前に参加者に共有しておきましょう。
参加者があらかじめ資料に目を通しておけば、前提知識を持って会議に挑んでもらえます。
議題について発言や補足をお願いしたい人には、あわせて根回ししておくと当日スムーズに会議が進行します。
5. 会議進行の台本作成
会議の台本を作成しておけば、当日の流れが大筋から外れる心配は必要ありません。
特に会議進行に不安がある場合は、台本を作っておくことをおすすめします。
台本は一言一句決めておく必要はありませんが、例文や議題をまとめておくと安心して会議を進行できます。
6. 進行のシミュレーション
作成した会議資料や台本を元に、進行のシミュレーションをしておきましょう。
シミュレーションのコツは以下の通りです。
例文を声に出して読む
タイムスケジュールを意識して行う
台本にスケジュールや質問案をメモしておく
当日の会議でハキハキ喋れるよう、例文は1度声に出してみることをおすすめします。
シミュレーションする際は各議題の議論に必要な時間を勘案し、台本に記入しておくと当日落ち着いて進行できます。
7. 会議のWebリンク発行・送付
近年ではZoomやMicrosoft Teamsといったツールを用いた、Web会議が主流になってきました。司会進行が会議のURLを発行する場合は、以下の手順で行いましょう。
Web会議を予約する
会議のURLを発行する
参加者にURLを共有する
あらかじめ参加者にWeb会議のリンクを共有しておくと、当日スムーズに接続できます。
議事次第の共有と合わせて会議URLを送付し日時をリマインドすれば、1度のやり取りで完結します。
会議当日の準備チェックリスト

必要な準備が抜けていると、そもそも会議を開催できません。
パソコンやプロジェクターなどの「機材準備」と、会場となる「会議室」の設営について、2つのチェックリストを準備したので活用してください。
機材については会議2日前には準備を完了しておくと、当日安心して司会進行できるでしょう。
【機材編】チェックリスト
会議当日に必要な機材は以下の通りです。
□ ホワイトボード □ マーカー □ パソコン □ プロジェクター □ マイク □ スピーカー □ ポインター □ 電源タップ □ 延長コード □ ボイスレコーダー |
マイクやスピーカーは、会議の前に音声チェックもしてください。
会議は必要な機材が多いため、電源タップや延長コードで電源を補いましょう。
機材がうまく接続できない場合もあるため、準備に30分ほど余裕があると安心です。
【会議室編】チェックリスト
会議室の設営に必要な準備は以下の通りです。
□ エアコンの温度設定 □ 机や椅子の設営 □ 必要機材の準備 □ 照明の調整 □ 機材の接続テスト □ 飲み物の用意 □ 資料の配布 |
エアコンは効くまでに時間がかかるので、まずは温度設定から行いましょう。
参加人数に合わせて机や椅子を用意し、それぞれの席に資料を配布します。
必要な機材は、会議開始時間までに接続チェックを行ない、プロジェクター画面の明るさ調整なども完了させておきましょう。
機材の準備や会場設営はやることが多いため、1人で抱え込まずに補助してもらえる社員を確保しておくと良いでしょう。
会議を進行する際に意識すべき3つのポイント
当日の会議中に意識してほしいポイントは、次の3つです。
時間を管理する
質問を投げかける
発言者以外にも目を配る
意義のある会議を行うためには、進行役が適切に場をコントロールして、参加者が集中して意見を出し合える環境を作ることが大切です。
時間を管理する
会議は時間内に終えることが大切です。時間がオーバーすると、参加者のモチベーションが下がり、結論が曖昧なまま終了してしまうこともあります。
会議を時間内に終えるためにも、以下のような対処をしましょう。
あらかじめ参加人数を絞っておく
時間内の議論だけで結論を出す
次回に持ち越す(会議が複数回になると負担になるため注意)
進行役が時間を意識して舵を取ることで、限られた時間でも充実した会議が行えます。
質問を投げかける
会議が停滞したり、参加者から意見が出にくいときは、進行役からの問いかけが会議を動かすきっかけになります。
例えば、次のような質問を意識すると効果的です。
Yes/Noで終わらないオープンクエスチョンを投げかける
専門性のある方に具体的に意見を求める(例:「この件について〇〇の視点からご意見いただけますか?」)
進行役は、参加者がなるべく具体的に発言できるような質問を投げかけましょう。質問力を磨くことで、会議の停滞を防ぎ、より深い議論を引き出せます。
発言者以外にも目を配る
全員が納得する結論を出すには、発言している人だけでなく場全体を見渡す必要があります。
特定の人だけが話し続けると、会議は偏った結論になりやすいため、なるべく全員に発言の機会を作りましょう。
具体的な工夫としては、次のような方法があります。
発言者以外の表情や姿勢を観察する
発言したそうな人がいたら、さりげなく話を振る
発言が偏っている場合は、内容をまとめ、他に違う視点がないか問いかける
こうした気配りを行うことで、一部の意見に偏らず、全員が主体的に発言できる会議になります。
関連記事:効率的な会議の進め方とは?基本の流れやスムーズに進めるコツを解説
シーン別!会議の司会進行で使える例文

会議の司会進行は場面に応じて言葉を発する機会が多いため、一連の流れの中でよく使う例文をまとめました。
このまま会議で使用できるフレーズなので、それぞれ確認しておきましょう。
「はじめの挨拶」の例文
会議は挨拶から始まります。
第一声は大きな声で、参加者全員に聞こえるようにはっきりと話しましょう。
「皆さまおはようございます。本日はお忙しい中、ご参加いただきありがとうございます。 時間になりましたので、これより〇〇会議を始めさせていただきます。 今回の会議の進行を務めさせていただきます□□部△△課の〇〇と申します。どうぞよろしくお願いいたし ます。 それではさっそく会議を始めさせていただきます。」 |
忙しい中会議のために時間を捻出してくれたことに対して、冒頭でお礼を述べましょう。
定刻になったことを告げて会議開始の宣誓を行った後に、忘れずに自己紹介してください。
「目的・議題・ゴールの確認」の例文
今回はどのような会議なのか、目的や議題、ゴールを確認します。
会議によって異なるため、事前に整理しておきましょう。
「お手元の議事次第をご確認ください。本日の会議では〇〇についてご意見を伺えればと思います。 (議題1)、(議題2)、(議題3)について議論を行い、この会議で□□を決定したいと思います。 皆さま積極的にご発言いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。」 |
会議を始める前に全員で目的や議題、ゴールを共有し、なんのために会議をしているのか共通認識を持てるようにしましょう。
これらを先に明示することで、会議が脱線するのを防げます。
関連記事:【テンプレート付】アジェンダとは?会議におけるメリット・正しい書き方・作成目的について解説
「時間管理」の例文
会議は、会議室の予約時間の関係で時間厳守が鉄則です。
限りある時間を有効活用するために、各議題の時間配分を伝えましょう。
「本日の会議は2時間を予定しております。議題は3つあるので各30分ずつ検討を行い、残りの30分はまとめの 時間といたします。 本日中に〇〇について決定できればと思っております。 私がタイムキーパーを務めますので、皆さまも時間内で議論を終えられるよう、ご協力のほどよろしくお願い いたします。」 |
だらだらと議論を進めても、まとまりがなくなってしまいます。
時間配分を伝えた上で、タイムキーパーの役割も担いましょう。
「ルール説明」の例文
会議を円滑に進めるには、ある程度のルールが必要です。
オンライン参加の方がいるorいない場合など、会議によってルールが異なるため、事前に周知しましょう。
「円滑な進行のために、いくつかルールを確認させてください。 まず、発言する際には挙手してからお願いいたします。挙手された方にマイクをお渡しするので発言いただければ と思います。Webにてご参加の皆さまは発言するとき以外はマイクのミュートをOFFにしていただき、発言の際に 挙手ボタンからお知らせください。 質疑応答は各議題の最後に時間を設けますので、その際にご質問いただければと思います。 こちらの会議室の使用は12時までとなっておりますため、スムーズな会議進行にご協力お願いいたします。」 |
オンライン会議に慣れていない人もいるので、ツールの使い方も含めてルールとしておきましょう。
会議終了時刻を伝えることで、建設的な議論を行いたい旨をアピールしてください。
「議題進行」の例文
会議は議事次第に沿って進めます。
関連資料がある場合は合わせてアナウンスしましょう。
「それではさっそく(議題1)に入りたいと思います。時間内に議論が終わらない場合でも次の議題へと移りま すため、時間厳守でお願いできればと思います。 お手元の資料1をご覧ください。こちらの補足説明を、〇〇さんお願いいたします。 この件についてご意見がある方は挙手にてお知らせください。」 |
何の議題について議論したいのか、明確に伝えます。
関連資料の紹介や担当者からの説明を行った後に、時間内に議論を終えられるようにしましょう。
「意見聴取」の例文
会議では参加者の意見を聴取するタイミングがいくつかあります。
発言の仕方を説明しましょう。
「ここで皆さまのご意見を伺いたいと思います。何かご意見やご質問がある方は、挙手をお願いいたします。 順番にお話しいただきますので、1人ずつ発言してください。 各発言について、他の参加者も補足や反対意見があれば、あわせてお知らせください。 さまざまな意見をお聞きし、皆さまと議論できればと思います。」 |
議事次第の通りに会議を進めるだけでなく、積極的に発言を促し広く意見を聴取しましょう。
活発な議論があってこそ、会議がより良いものとなります。
「会議のまとめ」の例文
会議終了5分前を目途に、今回の会議のまとめを行いましょう。
会議を総括する大切な場面です。
「会議終了時刻が近づいてまいりましたので、本会議での決議事項をまとめさせていただきます。 (議題1)では〇〇を、(議題2)では〇〇を、(議題3)では〇〇を行うことといたします。 後ほど資料と合わせて議事録を配信いたしますので、詳細は再度ご確認いただきますようお願いいたします。」 |
決定事項や今後の動きについて参加者全員が共通認識を持てるよう、必ず会議の振り返りを行ってください。
まとめをせずに会議が終わってしまうと、議論の内容があやふやになってしまいます。
「おわりの挨拶」の例文
会議の閉会を宣言します。
最後まで気を抜かずに、会議を締めてください。
「それではお時間になりましたので、以上で〇〇会議を終了させていただきます。 皆さまのご協力のおかげで、時間内にすべての議題について結論を出すことができました。ありがとうございます。 なお、次回会議は〇月〇日〇時から予定しております。詳細は後ほどメールにてお知らせいたしますので、 引き続きよろしくお願いいたします。」 |
会議終了時には、スムーズな進行に協力いただいた感謝の気持ちを伝えましょう。
次回会議の日程やそれまでのタスクがある場合は、この場でアナウンスしておいてください。
会議進行中のトラブルにも対応可能!困ったときに使える例文

会議を進行していると、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
そのようなときでも、とっさに使える例文を紹介します。
思うように会議が進まなくても慌てないように、あらかじめ想定しておきましょう。
「議論が脱線したとき」の例文
議論が活発になっている時ほど、収拾がつかなくなってしまいます。
会議ではよくあるシチュエーションです。
「活発な議論が進んでいるところ申し訳ございません。 この時間では〇〇について話し合っておりますため、〇〇についてのご発言をお願いいたします。」 |
議論が脱線した際は、本来の議題に沿った発言をするよう促します。
議題と関係ない話題に時間を使ってしまうと結論が出ない可能性があるため、できるだけ早めに軌道修正しましょう。
「意見が出ないとき」の例文
参加者からの質問やコメントがないと、会議を開催した意味がありません。
会議は意思決定の場であるため、議論を活発にするような進行をしましょう。
「皆さま、この件についてはどう思われますか? 少し意見が出にくいようですが、例えば〇〇に絞って考えてみると、何かご意見が出るかもしれません。 〇〇さんは、この分野について詳しいと伺っていますが、何かアイディアをお聞かせ願えないでしょうか? 他の方もぜひ遠慮せずにお話しください。」 |
意見が出ない際は、大枠ではなくピンポイントな事柄に絞って意見を収集してみましょう。
まずはその分野に詳しい人に意見を聞くことで、他の参加者も議題の解像度が上がり発言しやすくなります。
「意見が対立したとき」の例文
議論が活発化するあまり、意見が対立する場合もあります。
対立は悪いことではないので、双方の意見を詳しく聞いてみましょう。
「皆さま、貴重なご意見をありがとうございます。 現在、〇〇と□□の間で意見が対立していますが、それぞれの意見には利点と課題があるようです。 まず、〇〇を支持する理由をもう少し具体的に教えていただけますか?□□についても同様にその利点を 詳しく伺いたいと思います。 それぞれの意見を理解した上で、共通の解決策を見つけられるよう議論を深めましょう。」 |
意見が対立した際は、両者の言い分を具体的に聴取しメリットと課題を洗い出します。
それぞれの意見を聞いた上で、再度議論を再開してください。
「時間が押しているとき」の例文
会議は時間制限があるため、時間が押す場合があります。
そのまま議論しても時間が足りなくなるだけなので、折を見て中断してください。
「現在の議題について非常に活発な議論が続いていますが、あと5分で次の議題へと移らなければいけません。 ここで一度皆さまのご意見をまとめたいと思います。 本日中に結論が出ない場合は、次回会議にて引き続き検討する時間を設けます。」 |
時間が押している場合は議論をこれ以上進めず、これまでのまとめを行いましょう。
必要に応じて次回会議で再度議論することとすれば、参加者も納得してくれます。
会議終了後にやるべき3つのこと
会議が終わってホッとしたのも束の間、会議後にすべきことが3つあります。
議事録の作成や次回会議の調整を行い、次の会議に備えましょう。
また、今回の会議のフィードバックをしておくと、再度進行役を依頼された際に役立ちます。
議事録の作成・送付をする
会議終了後は内容を忘れないよう、できるだけ早いうちに議事録を作成しましょう。
録音データの文字起こしを行い、発言者を区別します。
発言の意図を誤ると結論が変わってしまうため、間違えないように正確な議事録を作成してください。
議事録の作成は、会議内容を記録する大切な業務です。
ミスをしては参加者に迷惑がかかってしまうため、文字起こしツールを活用し素早く正確な議事録を作成しましょう。
作成した議事録は上司や主な発言者に確認を取った後に、全参加者に送付してください。
次回会議の日程を調整する
引き続き会議を行う場合は、次回会議の日程調整が必要です。
あらかじめ日程が決定している際は、議事録の最後に記載しておきましょう。
日程が決まっていない場合は、以下の日時調整のコツを参考にしてください。
あらかじめ参加者のスケジュールを確認する
いくつか候補日時を提示する
議題の担当者や事情に詳しい人が参加できる日時にする
議事録の送付と合わせて候補日時をいくつか提示できるとスマートです。
フィードバックをもらう
会議の進行が終わったら、自身で振り返りを行いましょう。
「時間通りに進められなかった」「議論をうまく促せなかった」など反省点や改善点が出てくるはずです。
次回の会議はよりスムーズに進行できるよう、反省点や改善点を復習しておきましょう。
機会があれば上司からフィードバックをもらえると、自分では気づけなかった改善点がわかります。
自身の反省点と上司からのフィードバックを、次回の会議に活かしましょう。
良い会議を行うためには十分な事前準備しよう
会議の進行役(ファシリテーター)にとって最も大切なのは、事前にしっかりと準備をしておくことです。会議の前には、次の準備をしておきましょう。
時間配分を考える
台本を作成する
参加しやすい雰囲気を作る
会議後の議事録作成の準備をしておく
事前準備ができていれば、当日の仕切りや会議後の議事録作成・共有までがスムーズに行えるだけでなく、進行を務める方も落ち着いて会議に参加できます。
また限られた時間で充実した会議を行うためにも、進行役は時間を管理することが大切です。
AI議事録作成ツール『Rimo Voice』では、AI Botが会議終了5分前に通知を出し、決定事項を整理してくれる機能が搭載されています。

この機能により、次のようなメリットが得られます。
進行役は時間を気にする負担を軽減できる
参加者はメモを取る必要がないため、発言に集中できる
会議終了後の議事録も自動で作成できる
『Rimo Voice』は7日間の無料トライアルが用意しているため、関心のある方はぜひ気軽にお試しください。
登録には Googleアカウント・Microsoftアカウント・メールアドレスのいずれかが必要です。クレジットカードの登録は不要で、トライアル終了後は自動的に解約されるため安心して利用できます。
これらのAIツールも取り入れながら、自信を持って会議に臨めるよう、事前準備を整えていきましょう。
関連記事
タグ
- 会議関連
一覧に戻る